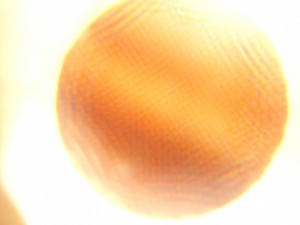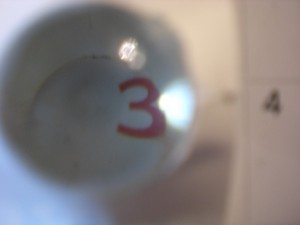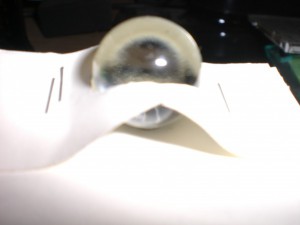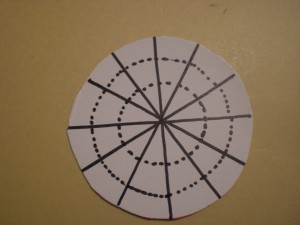キッチン・サイエンス 色の変わるドーナツ
手作り顕微鏡
- 2013年02月17日
- サイエンス
ビー玉顕微鏡
手作りで顕微鏡を作りましょう。かなりの精度です。
クリックしてみてね。茶色の印刷面がきれいな模様で見えますよ。
クリアーなビー玉が顕微鏡に変身するよ。
ちょっと離れるとこんなに見えます。ビー玉の大きさで、倍率は変わるよ。
ビー玉を大きくすると、ほら、3と4を比べてね
レンズ1個の単式顕微鏡です。
ビー玉は小さい方が倍率が高いよ。
作り方
1 名刺または名刺大の大きさの紙を半分におり、両方に穴あけパンチで
穴をあけます。
2 片方の穴を大きくします。ビー玉の大きさよりやや小さいくらいです。
3 ビー玉が穴の中心になるように置き、ホッチキスで留めます。
一口メモ![]()
レーウェンフックという人が考案した顕微鏡です。
彼は生涯500もの顕微鏡を作ったそうです。
小さなガラス玉を使うともっと倍率が上がり
200倍くらいまでになります。
]
変形ぶんぶんゴマ
- 2013年01月31日
- サイエンス
ビューーンビューーン!不思議音がするよ!
昔ながらのぶんぶんゴマを厚紙で変形してみました。
大きなボタンととこ糸でできます。
くるくる回したあとで、左右両方に糸を引いてね。
独特の音がします。
ぶんぶんゴマもびゅんびゅんゴマも、あっという間にできるよ!
いろいろ工夫して、音の変化を楽しんでね!
びゅんびゅんゴマは色の変化も楽しめます。
材料と作り方
材料
5センチ角の正方形の厚紙
タコ糸 80センチ
マジック(または、サインペン)好きな色2色以上
きり、または目打ち(穴をあけるため)
作り方
1厚紙に色をぬる。
2きりで厚紙の中央に穴を2つあける。
3たこ糸を片方から通し、戻ってくるようにとおし、結ぶ。
4厚紙に1センチ間隔で、7ミリの切り込みを入れ
たがいちがいに折る。
完成!
色を塗らぬらなくても、音は楽しめるよ!
遊び方
出来たら両手で糸を持ち、軽く10階から20回くらい
はさんだ厚紙を回してね。タコ糸を外に向かって引きコマを回転させます。
少し引いたら、内側にゆるめます。そしてまたひきます。
コマが動き続き、不思議な音も響き続くよ!
一口メモ![]()
ぶんぶんゴマは、江戸時代に流行ったおもちゃです。
古くは、竹で作られたそうです。強風が松林を抜けて
いくような音を発することから、《松風独楽》と呼ば
れて いたそうです。
音がするのは、回転しているものが空気を振動させて
要るからです。動いている物体が、ずっと動いていよ
うとする「慣性の法則」を利用しています。
これは、ぶんぶんゴマです。
ふしぎなコマ
- 2013年01月17日
- サイエンス
アラ不思議・・・・・なんで色がでてくるの?!
白黒のコマが回るとカラーに?!
回すと、
えっ?色が出てきたよ。
- 緑色がきれいだな
白黒のはずが、回すと色が出てきます。
緑色以外に、オレンジや赤、紫などが・・・。
写真にうつせるi色は限られていますが
いろいろ試してみてね。
つくりかた
白い厚めの紙に直径8センチの円を書き、
切り抜きます。
次のような模様を書いて、規則正しく黒く色を塗り
中心にようじをさします。
できあがり!
模様によって見える色が違うよ!
こんな模様はいかが?自分のオリジナルをつくってね!
一口メモ![]()
あたる光や回す方向で色が変わるよ。
写真は蛍光灯の下のものです。
乱発!紙コップロケット
- LINK
- ・日本成人病予防協会
- ・入間市青少年活動センター
- ・親業訓練協会
- PROFILE
- 金本佐紀子
- とにかく親子でサイエンス 代表
京都大学農学部卒(農業学士)。
香川大学付属中学校勤務を経て埼玉県公立中学校にて32年間教鞭をとる。2011年退職。 - 日本女子大学家政学研究科通信教育課程家政学専攻(学校教育領域)修了(家政学修士)。
日本女子大学教職教育開発センター客員研究員。
東京女学館大学専任講師。
- [ 現職 ]
» 多摩大学専任講師
- [ 社会貢献 ]
» 埼玉県ネットアドバイザー(2010年~2014年)
» 入間市健康福祉センター運営委員(2011年~2015年)
- [ 資格 ]
» 健康管理士 一般指導員
» 親業訓練協会インストラクター
- [ 所属学会 ]
» 日本教育制度学会
» 日本スクール・コンプライアンス学会
» 日本理科教育学会